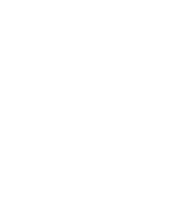
ココロはココロの望むまま。ワタシはワタシの望むまま。
カノジョはカノジョの望むまま。ミライという名のミチのまま。
スベテのモノが迎えるマツロ。ノゾミのままに、ワタシとカノジョはユメを燃やす。
そしてスベテが消えるまで。カノジョはそのユメを燃やしつくしていくのだろうか。
「ねぇねぇ、ラピちゃん。お淀の河川敷で、明日の夜花火しに行かない?」
………。突然の誘いに、ラピスはとりあえず2つの事を、咄嗟に思った。
その1。河川敷で、明日の夜花火しに行かない? というのは、ジパング語的に少し可
笑しいのではないだろうか。明日の夜、河川敷に花火をしに行かない? というのならま
だしもわかるのだが。もしくは河川敷で花火をしない? とするか。元々ジパング語が母
語ではないラピスにとって、こういう混ぜこぜ発想的な日常会話にはついつい、ツッコミ
を入れたくなってしまうのだった。
そしてその2。どうしてくぬぎは自分を誘うのだろう。おそらく他のメンバーは蒼潤に
鶫、悠夜といういつもの顔ぶれなのだろうが、花火となるとそれに保護者がついてくるの
が、とりあえずの決まりであると思う。兄弟である蒼潤と悠夜、その彼らの従姉妹である
鶫。親同士が友達だというくぬぎと彼ら。そういう、言わば身内同士が集まるイベントに
全く部外者である自分がどう入れと言うのだろうか…。
普通なら別に、こんな事は考えなくていいと思う。ただ自然に友達として加えてもらえ
ばいいのだし、自分が考え過ぎである事は自明の理だ。蒼潤の親とも鶫の親とも、くぬぎ
の親とも多少なりとの面識はある事だし。そもそも14歳になるかならないかの少女が、自
分は邪魔にならないかなどとまで考える必要はないと思う。
…ただ、その後。3つ目に思った事は。
「でもくーちゃん。私……花火、したことないよ」
「―え?」
意外な返答に目を丸くするくぬぎ。そう言えばくぬぎには言っていなかった。ラピスが花
火の類のイベントをあまり好いておらず、今までどちらかと言えば避けてきた事の根本的
な理由。
が、しかし。
「ちょうどいいじゃん! だったら初めての経験だから、きっと凄く楽しいよ♪」
何故かくぬぎにかかるとこうなってしまう。普段のくぬぎは寧ろ、こういうプラス思考よ
りも悲観的、妄想的なマイナス思考に向かって暴走する事が多いというのに……ラピスを
相手にするとどうしてか、そういう思考力がプラスの方向に反転するらしい。
「じゃあ明日の夜、7時にいつもの橋の下に集合だから! 待ってるからねー!」
参加不参加の返事をする前にくぬぎは駆けていってしまい、どうやらこれは、「行く」と
いう約束がいつの間にか成立してしまったようだ。
「……」
本気で断ろうと思えば、今からPHSでくぬぎに連絡をとる事も出来る。しかしそこまでして
断る理由を説明するのも何だか面倒くさい…という事は。
「とりあえず、行ってみるしかないってことかぁ…」
誘いの内容がどうであれ、やっぱり。誘ってもらった事自体は結構……嬉しかったから。
そうして今日も、京の街に吹く暖かい風が、ラピスの傍らを事も無く通り過ぎていく。
Atlas' ver_1.3(?)―――――――――――――――――――――――――――花火の夢
ラピス・シルファリーは一応、西の大陸出身の孤児だった。確か6歳の時に父が死に、
母はその後を追って自殺した。父親は一体どうしたわけか、炎の中で死んだという事だけ
は覚えているが。何があったのか未だにさっぱり、わからない。
6歳の頃の事だから無理もないとは思うが、首を吊ったらしい母の姿も、全くといって
いい程思い出せなかった。
『ラピス』というのは今の養父母が自分を引き取った時、彼女の髪がとても綺麗な瑠璃
色をしているというので、つけられた名前だ。両親が亡くなってから2年間、村中をたら
い回しにされていたラピスを見るに見かね、引き取った今の両親。多分実の両親よりずっ
とずっと、人間が出来ているヒト達だとラピスは思う。
「…あ、待て待て。人間じゃないんだから、人間が出来てるって言うのは可笑しいよね」
彼らは両方共何らかの、人間の形をしながら人間には無い力を持つ『千族』であるらしい。
この世界に住んでいる、千種あるとも言われる種族をまとめた呼び方―それが『千族』。
そんな彼らをラピスは怖がるどころか、内心とても歓迎した記憶がある。人間ではないと
いう彼らは、それなら――人間が持つ弱さや業からもきっと、解放されているのではと。
そんな錯覚を何処かに見てしまったからなのだろうか。
勿論、彼らには彼らの業があり、弱さがあり強さがある。彼らと共に過ごす内、少しず
つラピスにもそれがわかってきた。というよりラピスは、最近ではほとんど『千族』とし
か付き合いを持っていないような気もする。
今の両親に引き取られて、最初に出会ったのがくぬぎ。くぬぎは何故かは知らないが、
何かと当時の自分に関わりを持とうと声をかけてきたのだ。あの頃ラピスは今より相当荒
れていて、散々拒絶したにも関わらずくぬぎはへこたれなかった。そしてくぬぎの身内と
も言えそうな、性格的には硬派の蒼潤に、その弟で天才少年らしい悠夜。2人の従姉妹で
しっかり者の鶫。今のところ付き合いがあるこれらの人物は、おそらく全てが『千族』と
言える者達だ。彼ら自身が自覚しているかどうかは少し怪しいが、とにもかくにも純粋な
人間ではない。だから本当は、人間以上でも以下でもないラピスにとっては、住む世界が
違うはずの者達……――
いつかはきっと、同じ道を歩けなくなる時が来ると思う。同じ時間を生きられなくなる
だろうと思う。千族と人間では寿命の長さが違う事もよくあるというし、彼らは概して、
ある一定の年齢からはなかなか年をとらないものが多い。現に彼らの親は今も本当に若く
見えるし、ラピスの養父母も実年齢を聞くと、人間では有り得ないくらいに童顔と考える
しかない事になる。
それでも今だけは。彼らとずっと同じ所にいられるという夢を、見続けていたかった。
そして同時に。いつも心の何処かでくすぶって、それが何なのかはわからないけれど、
確かに存在しているもう一つの夢。二つの夢の間で揺らぎながら何とはなしに過ごす今の
生活を、ラピスは本当に…かけがえの無い夢だと思っていた。
「へーーー。花火ってアレだよな、火薬の塊に火つけて爆発させる奴!」
「その解釈はどうかと思うけど…良かったらユーオンも来てみない? くーちゃん達に紹
介するよ、私のお兄さんだって」
えぇー? ラピスの目前の金髪少年は、困ったように首を傾げてみせた。
ユオン・ドールド。ラピスの養父母が数ヶ月前、瀕死の状態で倒れていた所を保護した
精霊族の少年だ。彼には何故かその時以前の記憶が無く、何だかんだで結局ラピスと同様
拾われたという事になる。名前だけはっきりしているのは、とある占い師の占いの結果に
より、それが本当の名前なのかどうかもかなり怪しい。
ところで養父母が彼を拾う気になったのは、ある一つの理由からだった。それは…。
「いや……やめとく。ラピスの兄ちゃんだなんて紹介されたら本当に、オレが隠し子説の
誤解、更に定着しちゃうかもしれないだろ」
何処に。とツッコミを入れるのはとりあえずやめたラピスだった。大して付き合いも無い
夫婦のそんな事情を気にするような人種はおそらく、くぬぎ達の中にはいないと思うから
だ。
「まぁねぇ。ユーオンって本当、おとーさんにそっくりだもんね。おとーさんと違う種族
の千族じゃなかったら、多分既成事実にされちゃってただろうね」
何故かユオンは、ラピスの養父にそっくりな顔をしていたのだ。偶然と言えば全くの偶然
なのだろうが、それでもやはり多少なりと放っておけなくなるものだろう。元々お人好し
の両親2人だからこそ、尚更に。
「――ラピス。花火に行くって聞いたけど、本当?」
居間の方から養母がやってきた。
恐るべき若さの彼女の実年齢は、30を越えているはずだが。見た目は全く、20代前半に
したって童顔と思われそうな可憐な容姿の持ち主だ。
「大丈夫なの? 花火って一応、小さいけど火を沢山使ったイベントだから」
「多分、大丈夫だと思うよ。ほら、私確かに火はダメだけど、小さい火なら大丈夫だし。
大きい火でも火が出るってわかってればね」
父親が炎の中で死んだという記憶に関係するのだろうか…ラピスは火が苦手だった。
だからこそ今まで、花火などの火に関係したイベントとは無縁でやってきたのだ。
「もしも気分が悪くなったらすぐ連絡してね。いつでも迎えに行くから」
「有り難う、おかーさん」
……――? ラピスは自分の前で、何やら考え込んでいるユオンに気がついた。
「……ユーオン。何考えてるの?」
「えっ?」
「私の面倒見るためにやっぱりついてった方がいいんだろうか、とか、そんな事なら遠慮
するからね」
それを聞くとユオンは、たははは……と笑った。どうやら図星だったらしい。
「ラピスも色々大変だよな……何かオレに出来る事あったら、いつでも言ってくれよ」
「……うん。そうだね。ありがと、ユーオン」
「――? 何だよラピス、らしくねーぜ。いつもみたいに笑い飛ばして、ヒトの事考える
暇があったら、少しは精霊使う練習でもしてみれば? とか言ってくんなきゃなー」
……。珍しく素直に出てみると、返って向こうが不審に思うらしい。
「そうだね〜。ユーオンってば精霊族のくせに、精霊使えないんだもんね。これって致命
的な欠陥というか、最早精霊族の意味が全く無いというか。記憶が無くなる前もそうなら、
きっと精霊族一の恥さらしだったんじゃないかな? それを手がかりにすれば案外簡単に、
以前の自分の記憶が戻ってくるかもよ? 良かったねぇユーオン、とにかくわかりやすい
特徴があって♪」
「ひで……誰もそこまで言えなんて言ってないっつーの……」
始末が悪いのはラピスの場合、何の悪意も無いような笑顔で、上記の類の事をさらさらと
言ってしまえる点にある。
本人はあれでも自制しているらしいが、それだから尚のこと怖かったりする。
「さってと……そろそろ出なきゃ、時間に遅れちゃう」
簡単な荷物だけ持つと、夕暮れ時の空の下、ラピスは京都に向かって歩き出した。
お淀の川は今ラピスが住む所と京都の、ほぼ中間の場所にある。途中でワープゲートを
いくつか使わないと、本来なら徒歩で簡単に辿りつける場所では有り得ない。
「気をつけてね、ラピス」
どうやら養母が見送りに出てくれたらしい。一度振り返って大きく手を振ると、ラピスの
姿は夕暮れに消えていった。日没の遅い夏の夕暮れなのに、ラピスの深い青の髪も簡単に
飲み込まれてしまった。
*
「……ええっ? 子供だけで花火するの?」
目を丸くするラピスの横で、鶫が何やら地面に線をひいている。
鶫はラピスの認識から行けば、凄腕の陰陽師の娘だ。正確には陰陽師ではないらしいが、
陰陽師が使うような術はほぼ全て網羅しているらしいので、あまり変わらないと思う。
とりあえず今は、おそらく子供だけで火遊びをしても誰にも気付かれないための、簡単
な結界を作っているのだろう。
あまりそういう事を気にする性格には見えないが…知り合いに警備隊の者がいるらしく、
万一見つかった場合は色々言われそうでもあるので。という事らしい。
「こんな程度の火使うだけで大人の監督がいるなんて、バカバカしいと思わない?」
何かの文字が書かれた札を鶫が取り出すと、それは一振りしただけで火がついて、燃えて
消えていった。そんな光景に驚きもせずに、確かに…とラピスも思ったが。
それでもそういう決まりがあるのは、現に事故を起こした子供が過去にいるという事だ
ろう。鶫の言う「こんな程度の火」だって、使い方を誤れば惨事に繋がるのだ。どれだけ
自信があっても所詮は子供、馬鹿な事を仕出かす可能性は大人の数倍はある。だからこそ
決まりというものは、少々煩いくらいで本来は丁度いいのだ。それが無いと信じられない
くらい馬鹿な事をする者が、現にいるのだから。
まあ…そういう者は最初から、それがあっても無くても、する時には馬鹿をするのが、
お約束でもあろうが。
とはいえ、これらの認識が鶫達に当てはまるものでもない事もラピスはわかっている。
何しろたとえ、間違って火が草に燃え移ったりしても、力の1つや2つを使うだけで惨事
を未然に防ぐ事が出来る。それが千族なのだから。人間を基準とする細々とした決まりを
守る必要が無いのも、十分に納得出来た。
……などという事を鶫が持った札の火が消えていく間に考えているラピスは、自分の事
ながら相当…良く言えば思慮深い。普通に言えば考え過ぎだな、と、適当に感じていた。
「本当はアラス君が来てくれるはずだったんだけど、急に仕事が入ったとかで、僕達すっ
ぽかされちゃったんだ。あ、アラス君っていうのは蒼ちゃんのお父さんの友達でね。何で
も‘水代わり’ならオレが適任でしょーとかって言ってたんだけどさ〜」
くぬぎがにこにこと説明している横で、鶫が不満そうな顔をしていた。それが少しだけ気
になっていたのでラピスはあまり、マジメにくぬぎの話を聞いてはいなかった。
鶫にしてみればその誰かが来ていれば、結界を張るなどの手間をかけずに済んだので、
当然の事だろう。
ちなみに蒼潤の弟の悠夜も何かと忙しいらしく、今夜は参加していないようだ。
「ほらラピちゃん。こっちが手持ち、これがネズミ、あっちのが蛇花火。他にも色々ある
けど、わかりやすいのはこんな感じ。そこの線香花火は最後だからさっき言った奴の中で、
どれが一番やってみたい?」
「うーん……蛇、かなぁ」
花火がどんな物であるのかは、少しは調べていた。確か蛇花火というものはほとんど、火
を使っている感じがしない花火だったと思うのだ。
「蛇花火? よりによって一番地味な奴選ぶんだな、お前」
蒼潤が蛇花火をラピスに手渡しつつ、少し苦い顔をする。
「花火をやった事がないって言うなら、もう少し花火らしい花火をしてみろよ」
「いいじゃん蒼ちゃん、そんなの好き好きだよー。ほらラピちゃん、火」
くぬぎがひょいと、地面に置いた蛇花火に着火する。黒い小さな円柱型の蛇花火は、もこ
もこもこと体を伸ばし、うねうねとのたうちまわっていく……。
「うっわぁ……本当に地味だね〜……」
「だから言っただろ。花火としてはかなりの邪道だぞ、それ」
「蒼ちゃんみたいに、手持ちに10本位一気に火つけるのも、どうかと思うけど……今度は
こっちどう? ラピちゃん」
「うん。ありがと、くーちゃん」
何だかんだ言っても少しずつ色々な物をやってみると、1つの小さな火から様々な光が生
まれてくるのが、結構面白かった。炎というよりも光る花を見ている感じがする。花火と
いう名前の由来を、実体験をもって感じたラピスだった。
「……綺麗、だね。花火って」
「そうでしょ? 本当はこんなのまだまだ序の口で、夏の終わりの大きなお祭りで沢山の
大型花火が打ち上げられるんだ。今年は一緒に見に行こうよ」
「あ、ゴメン。多分夏の終わり頃はおかーさんの実家に里帰りしてると思うんだ」
「そうなの? 残念……ほんとに綺麗なんだけどなー」
あ、もう消えちゃったやと、くぬぎは新しい花火を取りにいく。そろそろ普通の花火は底
をついてきたようで、花火の終わりのお約束・線香花火の出番となった。
「あーあ……線香花火って綺麗だけど。これで終わりって感じが淋しいんだよね〜」
「……うん。他の派手なのと違って、儚い感じがするね」
まるで彼岸花のようなその光は、とても綺麗なのに……何故か淋しい。
でもそれは線香花火に限った事ではないと、ラピスは思った。
どの花火もその命とも言える火薬を、たった数秒の光のために一時に使い果たす。
花火の命を奪う火は、しかしそれが無ければ花火を生かす事すら永遠に有り得ない。
そして花火の命と共に、それ以上何をも奪う事なく……光と共に静かに消えていく。
「こういう、消えていく運命だけの炎って……綺麗、だね」
何だかそれは、花火に感動するというより。花火の在り方に心を動かしているようで、自
分の事ながらラピスは苦笑するしかなかった。
――炎の花など嫌と言う程見てきたから。
本当はそんなに覚えていないけれど、全てを奪い尽くす炎の凄惨さ………
その美しさに比べれば、こんなに小さな火は全く取るに足らない。
……あれ、とラピスは、ふと止まった。今自分は、確かに炎を美しいと思った。
本当の炎に比べたらこんな小さな火、どうって事はないと心から思っていた。
「……なーんだ。それじゃあ……」
「――? ラピちゃん?」
不思議な顔をするくぬぎにも気付かず、ラピスはじっと、手元の線香花火を見つめていた。
なーんだ……私、別に。炎が苦手なんじゃなくて、ただ好きだったのかな。
思わず惹きこまれてしまう程美しい炎の前では、体が動かなくなってしまう程に。
――その一瞬の感慨はしかし。誰かによって絶対的な否定を受けた。
違う。違う。違う。絶対に違う。お父さんを殺した炎なんかに、ワタシが惹かれるはず
なんてない。全てを奪って、奪い尽くして。そうして奪う事でしか、存在し続ける事が出
来ない炎なんか。こうして消えていく事こそ当然の炎の方がどれだけ、存在として綺麗な
のかしれないんだから。
儚い命を燃やす炎……そうして消えていく光。消えない炎なんて醜いだけだから………
だからこんなに、花火は綺麗なんだ……。
「…………」
とっくに消えてしまった線香花火を見つめたまま。ラピスはぼーっと外界を聞いていた。
まだ残っている花火を取りにいったくぬぎ。
来年はもっと沢山用意した方がいいかと考えている鶫。
する事がなくなったので剣の素振りを始める蒼潤。それを危ないと怒る鶫。
当てるわけないだろと言い返す蒼潤。最後の花火をラピスに渡して火をつけるくぬぎ。
またぼーっと消えていく光を見つめる自分。
そんな自分の横で同じ光を楽しそうに見つめるくぬぎ。
改めて少し離れた場所で剣を振る蒼潤。
いち早くゴミを集め出すしっかり者の鶫。
いつの間にか、当たり前にその中に混ぜてもらえていた……しかし異邦人のラピスは。
ただ、今この時の温かな気持ちと。穏やかな幸せに、ある事を願う―――
ああ…いいなぁ、こういうの。
ずっとこれが続けばいいのになぁ。
何があってもこのままの状態で。当たり前みたいに仲良く、いられればいいのに。
たとえば私が、今ここで。花火の光と一緒に消えてしまったとしても。
命を燃やして消え行く花火。それこそが綺麗な花火。
そうなってこそ、その存在が輝く花火。
だからそれこそ、花火の夢。花火が見た夢。消え行くための願い。
消え行く事こそが当たり前で、それ以上でもそれ以下でもなくて。
喜ばれるのに淋しくて。
けれど殊更に気にされる事もなくて。
それでもどうしてか、忘れられるという事もなくて…。
花火が見た夢のように、このまま消えちゃったらいいのに。
このままみんなと、一緒にいるまま。消えちゃったらいいのに。
そのまま消えても、みんなと一緒に。ここにいるままだったらいいのに。
気が付けばラピスは、くぬぎが鶫の方へとゴミを持っていった間にふらふらと…彼らか
ら少し離れた場所まで歩いてきていた。
「―? あれ? ラピちゃんは?」
ラピスの姿が無い事に気付いたくぬぎや、
「ちょっとその辺でも散歩してるんじゃない?」
見事にその状態を言い当てる鶫に、
「その内帰ってくるだろ。よくある事だしな」
適当に放っておいてくれる蒼潤。
この3人がいつまでもこういう風に、自分を見てくれていればいいのに。
ある日突然、私が消えても。殊更に心配もせず。かと言って完全に、放っておきもせず。
いつか帰ってくるだろうと、当たり前のように……いつ帰っても受け入れてくれて。
たとえいつまでたっても、帰ってくる事が有り得ない場合だったとしても……ずっと、
こういう風に思っていてくれたら。
そんな風にここから消えられたら…それはどれだけ、シアワセな事だろうと。
それが花火の見た夢。当たり前に消えていく願い。
当たり前に消えたとしても、忘れられる事もないような。そんな命。
悲しみも喜びも無くて、特別な感情は何1つなくて。
自分がここにいる時と同じ目で、消えた後も自分を見てくれる夢。
そんな風に消えてしまいたい命。消えていく事こそ自然だった炎。
…どうして今こんな事を考えるのか、ラピスには全くわからなかった。ここにいたいと
思いながら、ここから消えたいというその夢が確かに両立していた。
その夢はどう考えても矛盾して、自分の思いながら本当に訳がわからない。
「…でも私、ずっと…こう思ってたかもしれない……」
だからどうして、こんな事を考えて…そして涙が出てくるのか。ラピスには全くわから
なかった。―――わかってはいけない気がした。
「だってどうせ。いつか私は、消えるんだもの」
それがそう、遠くない日の運命である事を――
ラピスは知らずとも。誰かはずっと知っている。
ユメはいつか覚めるものだから。ユメをユメと知るならその運命をも知っているから。
ユメの終わりにスベテが消えて。ヒトは二度と同じユメを見ることはない。
覚めてしまえばもう二度と。決してこのユメには戻れない。
それならさっさと目覚めてしまえ。これ以上このユメにとらわれてはいけない。
どうせ消えるなら早く消えてしまえ。これ以上このユメを好きになってはいけない。
これ以上このユメにいたいと思ってしまったら……
これを失った時、ワタシはきっとカノジョに負けてしまう。
ワタシはきっと耐えられない。これを失えばワタシはワタシでいられなくなる。
―ラピスも色々大変だよな……何かオレに出来る事あったら、いつでも言ってくれよ―
それもひょっとしたら。もうとっくの昔に、手遅れかもしれないと知っての事なのか。
本当はそこまで陽気でないくせに、自分の前では何故か一際、明るい誰かの。
そこに不意に思い至ったラピスは。夜に溶けそうな瑠璃色の髪と青い目で空を見上げ。
そうして今夜は、京の街を通る冷たい風が。ラピスの傍らを唐突に吹き抜けていった。
了
−そしてアナタのヒが、わたしタチのメのマエからキえてしまったそのトキのために−
その少女が失ったものを、察していたのは。
おそらくその、自らを成す記憶を代償に、常なる哀しみを封じた青い目の――
青い髪の女性と。青い目自体を日頃は封じた、記憶のない誰かだけであり。
「………ねぇ、ラピス。花火って本当に、とてもキレイなものなんだけど」
青い目そのものを封じた誰かと、想いを分ける事も出来ず。女性は一人――その少女の、
彼女との闘いを思いながら、ただ哀しそうにする。
「消えてしまうからこそキレイなもので、ずっと燃えていたら、ただの火なんだって……
わかっているけれど」
それでも女性は願ってしまう。誰も知らないココロの奥深く、女性の知らない女性が、
覗き見たその夢。知ってしまった少女の本当の願い。
「キレイだけど……消えるからキレイなのはわかってるんだけど。ずっと見ていたいって
思うのは、我が侭なのかな?」
膝の上で眠る養女の、キレイな瑠璃色の髪を撫でてみる。
「ずっと消えないでいてほしいって思うのは……おかしいのかな」
――どうせこの子も、わたし自身ですら。
今こんな時間があった事を後で覚えてはいないのだろうけど。
それを知りながらついつい。その先も女性は口にしてしまう。
「ずっと、消えないでいたいって。花火だってそう願っちゃ……いけないのかな……」
―――キレイになんか、輝かなくたっていいから。
アナタにずっとココにいてホしいとネガってしまうわたしタチは、ワガママですか…?